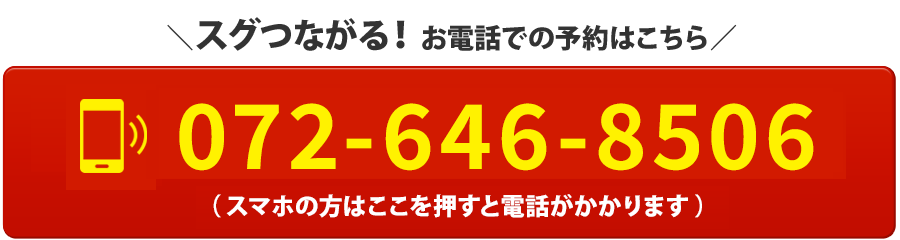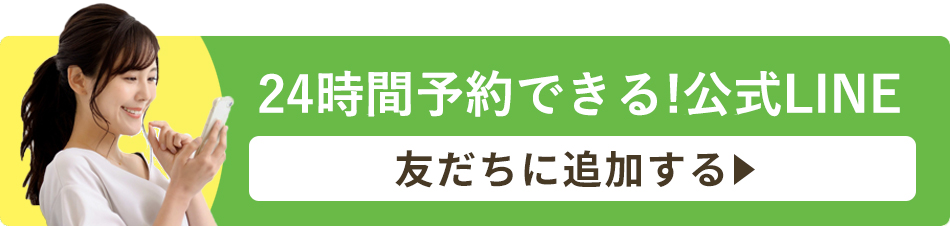野球肘
野球肘の原因

野球肘はピッチャーやキャッチャーに発症することが多く、オーバーユース(使い過ぎ)によって起こります。
一般的に、野球肘は内側・外側・後方に発症し、多くの場合は肘にストレスがかかり続けることによって痛みが出てきます。最も発症が多いのは肘の内側です。
主に上腕骨内側上顆炎・円回内筋付着部炎など筋肉や靱帯の牽引力が原因となって骨の障害が発症するものが多く、投球動作の際に手首の曲げ伸ばしを繰り返す事によって前腕の筋肉が硬くなることが肘のストレスの大きな原因の一つとなっています。
(小学生くらいの年齢では骨が完全に硬化していないため、軟骨障害や骨端線離解などが多い)
野球肘の特徴

野球肘に深く関わる筋肉は、リリースする瞬間に手首を手のひら側に曲げる働きをする屈筋群です。
屈筋群には橈側手根屈筋・尺側手根屈筋・長掌筋・浅指屈筋など複数ありますが、その中でも野球肘では“円回内筋”という筋肉が野球肘を引き起こしやすい筋肉です。
野球肘の最終段階では骨の損傷が起こることが多く、その発生機序の中で大きな原因となるのは繰り返し投球することによって酸欠状態に陥った筋肉の硬さです。
硬くなった筋肉は緊張度が高まるため、衝撃を吸収しきれなかったり伸び縮みが出来ないので結果的に骨への牽引力や負担が増加してしまいます。
また、投球を繰り返すことで筋肉への負担が蓄積され、筋肉にトリガーポイント(シコリ)が形成されて筋肉からも痛みが出てきます。
このトリガーポイントが連鎖的に痛みを拡大させ、さらに硬くなってしまうことで筋肉は血行が悪くなり酸欠状態に陥って肘全体に痛みを引き起こします。
この酸欠状態になり痛みを出してしまう状態を筋筋膜性疼痛症候群(MPS)といい、ひどい場合は痺れも伴います。
各年代で野球肘として肘の痛みを引き起こす背景にはこのように、骨だけでなく筋肉からくる痛みが深く関わっています。
当院の治療の方針

当院では、問診や運動学的検査を徹底して細かく行い直接原因となっている筋肉を見つけ出し、トリガーポイントが発生している筋肉に対して血流を改善させる施術を行い、根本的な原因を取り除いていきます。
さらに、施術効果を高めるためにマトリクスという特殊な機械を用いて施術を行います。
これにより痛みを和らげるだけではなく、硬くなっている筋肉や組織を柔らかくし、神経の伝達異常を正常化します。
筋肉の緊張がなくなることで、骨への牽引力も弱まり回復は次第に早くなっていきます。
また、痛みを繰り返さないようフォームの改善やストレッチ方法などもお伝えし、ご自身でも継続して実践できるようケア方法もお伝えしております。